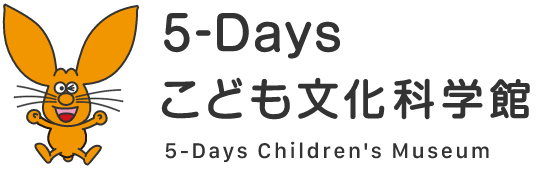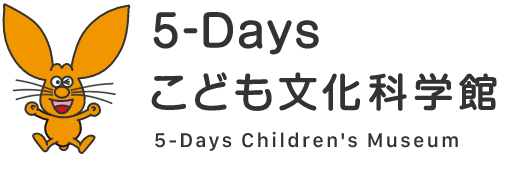ブログ
掲載日2025.07.20
2025.07.20
それはツノ?タケノコ?いいえ、貝です。
さて7月20日の科学教室。講師の野上光康先生が手にするのは・・・?
こちら、拡大してみました。これはツノでもタケノコでもなく「ビノスイガイ」。れっきとした貝です。
ティッシュの箱より大きいこの貝はラクダガイ。南の島で採れたもの。

そんな珍しい貝の標本を多数観察後、こどもたちは身近な貝(なんと「生きた」貝!)の標本づくりに挑戦!そう、今回の科学教室は「貝の標本作ってみないカイ?」なのでした(^^)


アサリガイ。貝殻の隙間からカッターナイフを差し込んで貝柱の部分を切り落とし、開いて身を取り出します。


サザエ。一度茹でてから、細長い針を使って身を取り出します。
途中で身がちぎれて、貝殻の奥に残ってしまわないよう、慎重に・・・!

ほかにもバイガイ、ハマグリなど様々な貝から身を外しました。
(ちなみに、身の部分はこどもたちが美味しくありがたくいただきました。)
そのあとは歯ブラシなどを使い貝殻の内側をきれいにして、水気を切ります。
二枚貝の仲間は貝殻がばらばらにならないよう糸で縛りました。
本日の教室での作業はここまで。あとはお家でしっかり乾燥させて完成させます。
今回の科学教室で、様々な貝の種類や習性を知り、実際に貝を触って構造を確かめたりしたこどもたち。これから貝を食べるときには、ちょっぴり見方が変わるのではないかな?
こどもたちをやさしくわかりやすく指導してくださった野上先生、ありがとうございました。